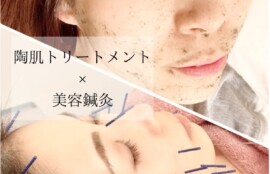なぜか冬になると疲れやすい、やる気が出ない…
みなさん、こんばんは☺️
先日紅葉を楽しみながら登山に行ってきました⛰️
11月になり、風も寒くなってきましたね。
私は最近布団から出るのが辛いです。
元々寒さと朝が弱いのもあるのかも。。。
当院に通ってくださっている患者様からも
「最近、朝起きるのがつらい」
「仕事に集中できない」
「夏より疲れが抜けない気がする」
冬になると、こんな声をよく耳にします。
夏バテという言葉はよく聞きますが、実は冬にも体調を崩しやすい時期があるのをご存知でしょうか。
特にオフィスで働く方々からは、「なんとなくだるい」「やる気が湧かない」といった、病院に行くほどではないけれど確かに感じる不調の相談が増えます。
この冬特有の疲労感やだるさ、実は東洋医学の視点から見ると、とても理にかなった体の反応なんです。
冬の疲労感、東洋医学ではこう考える
東洋医学では、季節と人間の体は密接に関係していると考えられています。
冬は「蔵(ぞう)」の季節、つまりエネルギーを蓄える時期とされています。
自然界の動植物が冬眠や休眠に入るように、人間の体も本来はペースを落として休息を求める季節なのです。
ところが現代社会では、季節に関係なく同じペースで働き続けることが求められます。
夏も冬も変わらない業務量、変わらない通勤時間、変わらない労働時間。体が「休みたい」と言っているのに、そのサインを無視して働き続けてしまうことで、さまざまな不調が現れてきます。
冬に現れやすい不調のサイン
- 朝起きるのがつらい、目覚めが悪い
- 日中の眠気が強い
- 集中力が続かない
- やる気が湧いてこない
- 疲労感が抜けない
- 体が重く感じる
- 些細なことでイライラする
これらは「冬バテ」とも呼べる状態です。
「冷え」と「気の不足」が疲労を招く
東洋医学では、冬の不調を引き起こす大きな要因として「冷え」と「気の不足」を重視します。
1. 寒さによる「冷え」
冬の寒さは、体の表面だけでなく深部まで冷やします。
特に足元や腰回りが冷えると、全身の血流が滞りやすくなります。
銀座のオフィス街では、通勤時の冷たい風に当たり、オフィスでは足元が冷える空調環境で長時間過ごす、という方も多いのではないでしょうか。
東洋医学では「冷えは万病のもと」と言われるほど、体の不調と深く関わっています。
冷えによって血の巡りが悪くなると、筋肉は硬くなり、内臓の働きも鈍くなります。
その結果、疲労物質が体に溜まりやすくなり、慢性的なだるさにつながるのです。
2. 「気」の消耗
東洋医学でいう「気」とは、生命活動を支えるエネルギーのようなもの。
この気が不足すると、やる気が出ない、疲れやすい、免疫力が低下するといった状態になります。
冬は日照時間が短く、朝も暗いうちに起きて、夜も早く暗くなります。
この日照不足は、体内時計を乱し、気の巡りを滞らせる要因になります。
さらに、年末年始の忙しさや、一年の疲れの蓄積が重なることで、気はどんどん消耗していきます。
五臓の「腎」が弱る季節
東洋医学の五臓六腑の考え方では、冬は「腎(じん)」が影響を受けやすい季節とされています。
腎は、生命エネルギーの根源を蓄える大切な臓器。現代医学でいう腎臓だけでなく、生殖機能、ホルモンバランス、老化、そしてやる気や意欲といった精神面にも深く関わっています。
冬の寒さや過労によって腎が弱ると、以下のような症状が現れやすくなります。
- 慢性的な疲労感
- 腰や膝のだるさ、痛み
- 冷え性の悪化
- 頻尿や夜間頻尿
- 耳鳴り
- 気力の低下
「なんとなく調子が悪い」という状態の背景には、この腎の弱りが隠れていることが少なくありません。
生活リズムの乱れも大きな要因
現代の働く環境では、生活リズムが崩れやすくなっています。
- 残業続きで睡眠時間が不規則
- 夜遅い食事が続く
- 休日と平日の起床時間が大きく違う
- スマートフォンで夜遅くまで光を浴びる
こうした不規則な生活は、東洋医学でいう「陰陽のバランス」を崩します。
本来、人間の体は太陽のリズムに合わせて動くようにできています。
日が昇れば活動的に(陽)、日が沈めば休息へ(陰)。ところが現代社会では、夜でも明るい環境で活動を続けることができてしまいます。
特に冬は、ただでさえ体が「陰」に傾きやすい季節。
ここに生活リズムの乱れが加わると、体はさらに混乱し、疲労感や気力の低下として現れてくるのです。
冬の疲労は「体からのメッセージ」
「疲れやすい」「やる気が出ない」という状態は、決してあなたの気持ちの問題ではありません。
東洋医学的に見れば、それは体が発している大切なメッセージなのです。
「今、無理をしていませんか?」
「休息が足りていませんか?」
「体が冷えていませんか?」
こうした体の声に耳を傾けることが、不調を長引かせないための第一歩です。
鍼灸でできること
鍼灸治療では、こうした冬特有の不調に対して、体全体のバランスを整えるアプローチを行います。
- 冷えて滞った血の巡りを促す
- 消耗した気を補う
- 弱った腎の働きをサポートする
- 自律神経のバランスを整える
一人ひとりの体質や生活環境、不調の現れ方に合わせて、ツボを選び、体の本来持っている回復力を引き出していきます。
「病院に行くほどではないけれど、なんとなく調子が悪い」
「疲れが取れなくて、仕事のパフォーマンスが落ちている気がする」
そんな時こそ、東洋医学の視点から体を見つめ直してみませんか?
まとめ
冬の疲労感や気力の低下は、決して珍しいことではありません。
むしろ、季節の変化に体が反応しているサインです。
- 冬は本来「休息」を求める季節
- 寒さと気の不足が疲労を招く
- 腎の弱りが冬の不調と深く関わる
- 生活リズムの乱れが症状を悪化させる
東洋医学では、こうした不調を「体全体のバランスの乱れ」として捉え、根本からアプローチしていきます。
銀座という場所柄、日々忙しく働かれている方も多いと思います。
だからこそ、ご自身の体の声に少し耳を傾けてみてください。
冬の疲れを引きずったまま春を迎えるのではなく、今のうちに体を整えておくことが、一年を通して元気に過ごすための大切な一歩になります。